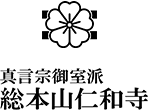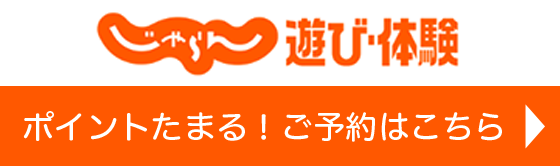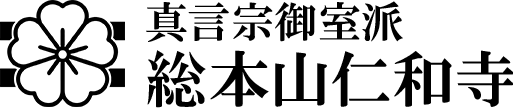心は明るさを好む

お寺の庭に桔梗(ききょう)の花が咲きました・・・本堂の片隅に紫の桔梗の花が、全て陽の当たる方向を向いて咲いていました。
このように花でも明るい方向を好むように、人間も又明るく、正しく、仲の良いことが好きなのです。こうした心を仏教では仏の性質と書いて仏性(ぶっしょう)と呼び、元々誰もが持っているというのです。
その心が素直にいつも表に出れば問題ないのですが、私たちの心にはそれを出せない働きもあり、それを・・・煩悩と呼んでいます。
つまり、私たちの心の中には仏様のような心と、それを妨げる心の二つがあります。
それが、悲しいかな~現実には妨げる心の方が強く、しかもその心に気づかないことが多いのです。工場の多い所では煙突から煙りをモクモク出し、大気を汚染している姿を見るとき、私たちも知らず知らずのうちに心の悪臭を周囲にばらまいて迷惑をかけているのかも知れません。♯「おびただしき煙は吐けど 我が罪は消してくれぬ ゴミ焼却炉」♯という歌もあります。
私たちが出した心の罪は見えないかも知れませんが、決して消されるものではありませんが~しかし、信仰によりみ仏は許して下さるのです。あたかも桔梗の花が太陽の方向を向くように、私たちもみ仏の方向を向いた生き方、つまり信仰を持った生き方をする時、明るい
み仏のお慈悲の心を感じ取ることが出来るのです。
お互い仏性(ぶっしょう)と煩悩(ぼんのう)を合わせ持つことに気づき、信仰により、安らかな生き方をしていきたいものですね・・・
私が子供の頃、誰かに向かって人差し指を向けると、お母さんや、おばあさんは、それは、してはならないことだと、しつけられた人は、少なくないのではないでしょうか・・・・
しかし、なぜ人差し指を人に向けてはならないか、ということについて、教えられた方やお考えになった方は、あまりないようです。
私も、最近まで、その教えに何の疑問も抱かずにいました。
ところが、「あの人は」と自分の手で人を指す形を作ってみたら、中指、薬指、小指の三本の指が、私自身の方を指しているではありませんか・・・・ある方にこんなことを教えていただきました。
一本の指で人を指すからには、その人を見る以前に、自分のことを、三倍は反省しなければならない。自分のことを反省すると、とてもとても人のことなど、とやかくいえるものではない。
だから、人差し指で人を指し示すことが、ただ漠然と悪いのではなく、自分のことをさておいて、人を取り上げようとする姿勢が、悪いのである。・・・ということでした。
まさに「人のふり見て、わがふり直せ」のことわざそのものの教えです。人を指し示し、見ようとする時、その眼は、その指は、私たちの心の鏡でなくてはなりません。
子供の頃、親からしつけられたことの意味が、何十年も経って、ようやく解った私でありました。どんな時にも、自分を省みる心のゆとりをもって、人に接したいものです。
笑顔の数が~幸せの数・良い言葉ですね・・・ではまた