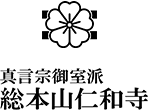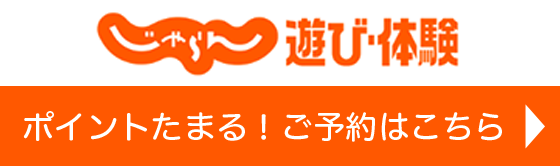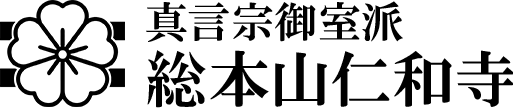がまん

我慢といえば、山形県に貧しい寒村に生まれた~「おしん」を思い浮かべます。泉ピン子さんの熱演に胸が熱く思い出されます。
我慢は庶民の合いことばであり、日本を支えてきた力でもありました。戦後80年という節目を迎えた昨今、戦争を体験された方々のことばの中に~「欲しがらない・勝つまでは」は~戦争中のスローガンと聞いて来ました。
戦後の日本は「欧米に追いつけ、追い越せ」の原動力になったのが「我慢」であった。その我慢も、現代では我慢をしないでよい豊かさの中に放り込まれた国民になってしまったのでしょうか・・・・
仏教でいう我慢は、諸悪の根源とでもいうような悪い意味で満ちていました。
もともと仏教の命題は「我」(が)のコントロールにあって、欲望の固まりである「我愛(我執)」(がしゅう)を徹底的に排除して、「滅我(滅度)」の精神的安定を得る宗教であります。
よい意味でも悪い意味でも人は自己中心です。動物も植物もこの自己中心性によって種族を繁栄させ、生き残ってきたのですから、むげに否定はできません。
そこで、仏教では自己を確立させて欲望を鎮め、多くの人間と協調して平和に生きることを目指します。その協調を壊すものが「慢」(まん)という~「おれガ・自分ガ」の~おごりの心に七つあります。
①「慢」は劣った人に対して、自分が勝っていると思うこころ。②「過慢」勝っている他人に対して、等しいと思うこころ ③「慢過慢」勝っている人より、さらに勝っていると思うこころ ④「我慢」自身の永遠を過信して、自分だけのものと執着するこころ。 ⑤「増上慢」悟っていないのに悟ったと思っているこころ ⑥「卑下慢」劣っていると見せかけて、本心とは違うこころ ⑦「邪慢」悪を正当化するおごりのこころ・・・こうして見ると「我慢」が一番の悪者のようです。
しかし、我れ自身が強いということは、別の意味では生きる力が旺盛なのであります・・・生への執着が激しいのでガンバリがききます・・・そこから辛抱する・堪え忍ぶという意味が出てきたようです。
ある日、仁和寺に台湾のバスガイドさんが参拝された折の事でした~「日本に3Kというのがあると聞きましたが、台湾にもありますよ」・・・と言われました。・・・「台湾はきつい、きたない、あつい、の2KAです。台湾では給料が一番良いのですが、この仕事の希望者がありません」・・・と言われ~どの国の人も、楽な仕事を好むようですね~と笑っていました。
そこで、社会で活躍している人達を見ますと、経済的に苦しい下積みの生活が長く、泣きながら、苦労とたたかい、努力、精進され、その結果成功された人達が多いようです。
釈尊がおっしゃられた言葉に「人生は苦しみであり、その苦しみに堪えてこそ人生がある。我慢の教えが仏教であり、苦しみこそが、私を人間らしく育ててくれる」と、お説きになっています。
人生には三通りの生き方があると~云われています。その三つとは、⓵蟻(あり)、⓶蜘(くも)、⓷蜂(はち)の生き方です。
⓵、蟻は自分の身体を保つため、どんな物でも貪欲に食し、他をかえりみない生き方です。⓶、蜘は、糸を張って獲物のかかるのを待つという、労少なく、功多くを求め、欲望的、打算的な生き方です。⓷、蜂は、花を選び、花をそこなわず、痛めず、蜜を求め、自分の能力を十分に生かし、何かをつくり出す~つまり蜂蜜を造り出す生き方です。
あなたはどの生き方を選びますか・・・
きっと~他人を侵さず、傷つけず、自分の能力を生かし、何かを創造し、他人のために報いる生き方ではないでしょうか・・・・。
きれいで美しい蓮の花は、どろ沼の中で育ち~泥を栄養として大輪を咲かせます・・・・そんな自分でありたい。
ひたすら合掌