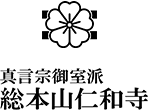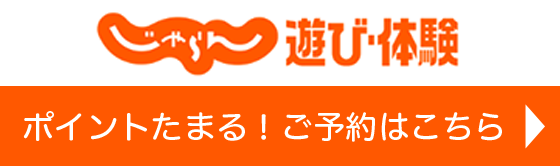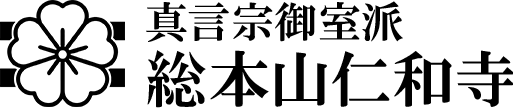見えぬもの

「暑い~暑い」といい暮らすうちに、もう秋の風が吹き始めて来ました。
そんな時~フト~こんな歌が聞こえて来ました・・・・
♫「村のはずれの、お地蔵さんはみてござる・・・いつもにこにこ見てござる」~〖曲名・みてござる〗~終戦直後、山上武夫作詞・海沼 實(みのる)作曲の童謡でした。♬ 〽
お地蔵さまと言えば、実は閻魔仏(えんまぶつ)でもあるのです。
皆さまが良く知られている地蔵とは「地蔵菩薩」のことでお釈迦さまが入滅後、弥勒菩薩が出現するまでの仏のいない世にあって、私達を導いて下さる菩薩の事なのです。その中でも「六地蔵」は、六道のそれぞれにあって衆生を救済すると言われる地蔵菩薩であり、私達を救うために六体の分身に当てて信仰されています。
このお地蔵さまは「延命地蔵経」という経典によれば「地蔵十徳」と言われる十種の福徳が信仰する人々に与えられると説かれています。
先ず、①女人泰産「安産と丈夫な子」、②身根具足「健全な身体」、③除衆病疾「病気・災難を除く」、④寿命長遠「天命を全うする」、⑤聡明智恵「すべてがわかる智恵をうる」、⑥財宝充溢(じゅういつ)「財産が充満」、⑦衆人愛敬「笑顔で接す」、⑧穀米成就「五穀豊作で困らない」、⑨神明(しんみょう)加護「神仏が災難も加護」、⑩証大菩提「悟りを啓(ひら)く」。これがお地蔵さまの十徳と言われるものです。
私達の日々の生活で求めてやまない徳ですが~目に見えるものではなく、心に感じるものが拠り所であり、祈りと信仰なのです。
大正時代の頃、金子みすずという童謡詩人がおられました。
金子みすずは、山口県長門市に生まれ昭和5年、27歳の若さでお浄土へ旅立たれた有名な詩人でした。西条八十先生からも、「若き童謡詩人の巨星」とまで称賛されています。
その童謡の一つに⁑「お魚」⁑という詩に〽【海の魚はかわいそう/お米は人につくられる/牛は牧場で飼われてる/鯉もお池でふをもらう/けれど海のお魚は/なんにも世話にならないし/いたずら一つしないのに/こうして私に食べられる/ほんとに魚はかわいそう】〽と唄っています。
今一つ⁑「星」⁑という詩に〽【青いお空のそこにふかく/海の小石のそのように/夜がくるまでしずんでる/昼のお星は目に見えぬ/見えぬけれどもあるんだよ/見えぬものでもあるんだよ】〽がありました。
このような詩に、作者の、ものに対する思いの深さ、心のやさしさを感じます。金子みすずの童謡は、小さいもの、力の弱いもの、名もないもの、あたりまえと思われるものの中に、尊いものを~とらえて唄っているように感じます。
☀【昼のお星は目に見えぬ/見えぬけれどもあるんだよ/見えぬものでもあるんだよ】〽と唄っていることばにも、尊い心のひびきがあります。
私たちは目に見えぬものはないと思いがちですが~しかし、私たちの目には、真っ暗闇の中では何も見えません。
光をいただいてはじめて見えるものです。
目が見えるのも光のおかげですが~慈悲の光は目には見えないものです。
しかし、目に見えないものではなく、見えぬもの~であるのです。それは、実は尊く心にいただくものであると思うのです。
秋の夜長~心しずかに見えないものを~夜空を見あげて・・・・ 〽 ではまた