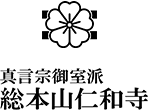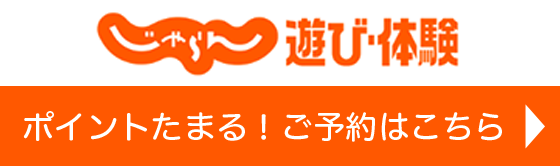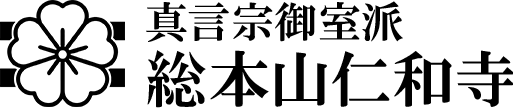喜んで捨てる姿(躾)は美しい

先日~「・・ここにゴミを捨てないで下さい・・」、と大きな文字で書かれた看板が立っている所へ、粗大ゴミを捨てている人に出会いました。なんということか、その方の人格を疑いました・・・
生活とは何か、社会とは何か、人間とは何か、全く解っていないこの人を腹立たしく思いました。
この世の中、命あるものは全て、独りでは生きて生けないものです。自分勝手の気まま生活は、人間の死を意味します。生きものは全て、他のものから多くの恩恵を受けながら、生かされて、生きているのです。私たちは社会人として、一人前になるためには、慣習、礼儀をしっかり身につけなければなりません。
「鳴く声の 良きも悪しきも 母鳥の 躾によるぞ 谷のうぐいす」と和歌にあるように、躾は大切な社会の教えです。
躾の語源は元来、農業に使われた用語で、田植における共同作業の大切さを身につけさせ一人前の成人にするため、未成年者の生活における基本的習慣、排出、睡眠、食事、着衣、清潔などの躾を教え、また農業以外一般の若者も男女を問わず、古来は奉公によって躾を鍛えられたものでした。
あるお経文に「身を整(ととの)え 口(くち)を正し 意(こころ)を誠にし 常に無常の理(ことわ)りを 忘るること勿(なか)れ」と説かれています。自分の行いは真実に生き、間違って思い違いをしてはなりません。自分を自覚し、価値ある生き方の出来る人となるための努力、それが躾(しつけ)ではないでしょうか・・・・
〽 もの持たぬ たもとは軽し 夕涼み 〽
この詩(うた)は、ものでも知識でも、たくさん集めたり持っていることが、かえって自分を苦しめたり不自由をもたらすこともあるというのです。
例えば、家財道具や食料品なども、集め求めすぎて、その居場所に困ったり、あげくに家族の争いの種になることさえある。物だけではありません、病気や性の知識があり過ぎて、必要以上に悩んだり迷ったりしている人も決して少なくありません。
まさに「・・過ぎたるは及ばざるがごとし・・」です。
そこで、ひとつ提案があります。この辺でお互いが「求める」「集める」という発想を「求めない」「捨てる」という方向に180度転換してみたら如何なものでしょうか。仏教には「喜捨(きしゃ)」という言葉がありますが、その意味するところは「喜んで布施をする」という~功徳を教えているのですが、同時に読んで字の如く「捨てる喜び」を知ることでもあるのです。
便利さを求めて集めたものが、かえって生きる邪魔にならないように、物でも知識でも余分に集める愚かさに気付き、むしろそうした「ぜい肉」を削りとって、いわゆるスリムになってみたらどんなにか楽になることでしょう。
そこで一句 ~ ☂ バイキング 欲張りすぎて 食べ残し ☂
来るお盆の食事は、ご先祖さまと我々との唯一のご縁です。ほどホドに頂きましょう。
ホドが越えると・・・心配しています。
*暑さに負けないように・暑中お見舞い申し上げます*
では~また・・・合掌